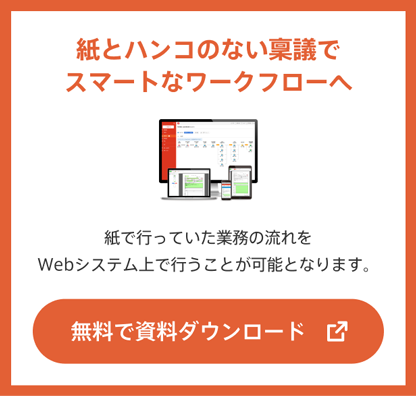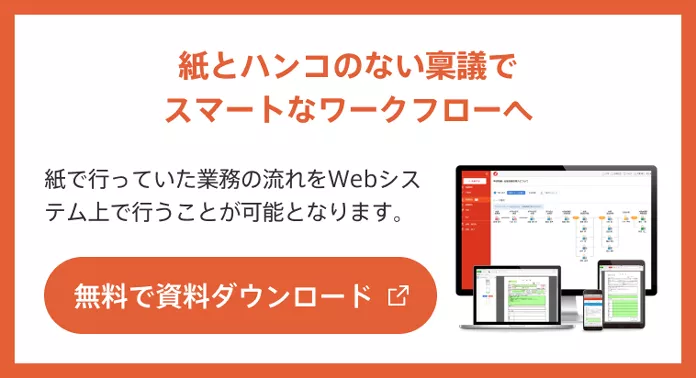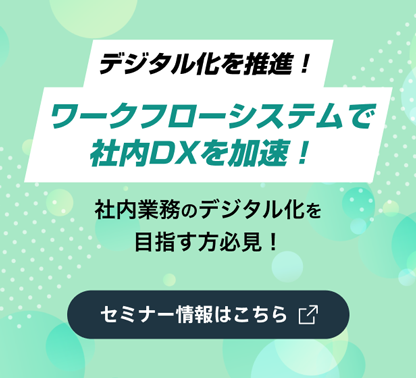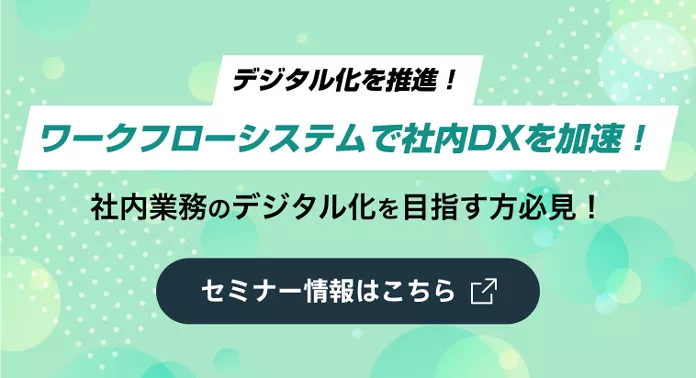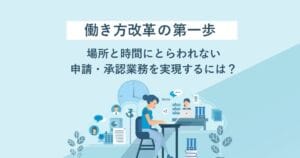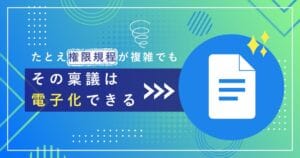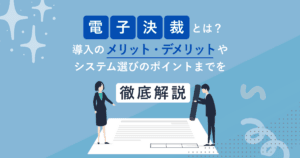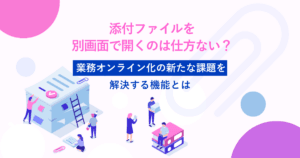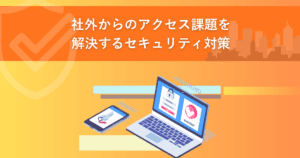テレワークを成功に導く業務の見直しポイントとは
インターネット・モバイル端末を利用し、自宅やコワーキングスペースなどで働く「テレワーク」。
働き方改革の一環として「働きやすさ向上のための雇用形態の多様化」や「ワーク・ライフ・バランスの実現」「人手不足の解消」などを目的とし、総務省や東京都などの自治体も先立って推進しています。
さらに、渦中の新型コロナウィルスの影響による企業の感染拡大防止や東京オリンピック開催など有事においては、事業継続の対応策としても注目されています。
テレワークとは
テレワークとは、ICT技術 (Information and Communication Technology/情報通信技術)により、一定の場所や時間にとらわれずに業務を行うことを指します。「テレ(tele)=離れたところ」と「work=働く」をあわせた造語です。また、テレワークに従事する人を「テレワーカー」と呼びます。
テレワーカーは、主にパソコンやモバイル端末を利用する業務が中心となる職種が向いており、次のような勤務形態で従事しています。
- 在宅勤務
基本的に自宅を仕事場とする働き方。PCとインターネット、電話、ファックスを利用して業務を行います。子育てや介護、障害などの理由によりこの働き方を選択する人が多く、通勤が不要になるために空いた時間の有効活用や通勤に困難をきたす人でも就業が可能。 - モバイルワークノート
PCやスマートフォンを利用して移動中や出張先などの外出時でも業務を行える環境が整っている働き方。営業など終日外出することの多い職種の人は、次の訪問時刻までの隙間時間を有効活用できる。 - サテライトオフィス勤務
レンタルオフィスやスポットオフィスなどの勤務先以外のスペースを仕事場として利用する働き方。本社が都市部にある企業は郊外に、反対に地方企業は都市部にサテライトオフィスを設置していることがある。
参考:一般社団法人 日本テレワーク協会 Webサイト『テレワークとは』(2020年4月20日)
テレワークの課題
国土交通省が行った平成30年テレワーク人口実態調査において、テレワーク制度の導入企業数は上昇傾向にあることがわかりました。
さらに新型コロナウイルスの感染拡大を機に、出社を控えて在宅勤務を中心とした業務へとシフトした企業も多く、事業継続が可能となった企業の経営者や社員はそのメリットを享受しています。
しかし一方で、テレワークに向いている業務であっても、オフィスに従業員が常駐しないことで次のような課題が生じるため、それをどうクリアしてくかをそれぞれの企業にあわせて考える必要があります。
- コミュニケーションがとりづらい
オフィスで直接顔を合わせる機会が非常に少なくなり、同僚や上司とのコミュニケーションのとりにくさから孤独を感じたり、不安になるケースがあります。解決策としては、Web会議システムやチャットなどのオンラインツールを活用し、定期的にミーティングなどで会話をする機会を作り、信頼関係を築くしくみをつくることが大切です。 - 勤怠管理が把握しにくい
出社している従業員とは異なり、テレワーカーの残業や業務開始・終了・休憩時間などの労働実態は出勤状況を直接確認できないため、どうしても不透明になりがちです。労働実態を正確に把握し、社内の従業員と同じ条件で管理するために勤怠やスケジュールを関係者が管理できる環境を整えることも必要です。また、労働時間・働き方に関するルール作りも徹底しましょう。 - 情報セキュリティにリスクがある
インターネットやモバイル端末が欠かせないテレワークには、情報セキュリティ上のリスクにも備えなければなりません。社員が外部に情報を持ち出す機会が非常に増え、情報漏えいや端末の紛失・盗難のリスクも高まります。それらの対策としては、社内のセキュリティポリシーに準拠した利用の周知徹底のほかに、テレワーカー向けの研修を開き、これらのリスクマネジメントの指導を行うと良いでしょう。
テレワーク推進を阻む紙の書類の課題とは
上記以外にも、新型コロナウイルス感染対策のために急遽テレワークを実施した企業の課題のひとつとして紙の業務が注目されています。
例えば、紙の書類への押印が必要な場合、会社印や上司印は職場にしか存在しないため、当然ながらテレワークで書類を完成させることはできません。書類を作成し、印刷をする、そして関係者の押印をもらう、という対面による紙の手渡しが発生します。これでは出社を余儀なくされることになるでしょう。
このような書類作成から申請、承認、保管までのプロセスをペーパーレス化できるとしたら、企業にとってどのようなメリットがあるでしょうか。
従業員が遠隔地で働いていてもスピーディーに組織的な意思決定が可能となります。また、いつでも承認の処理状況の確認が出来る、過去書類の証跡が確認ができるといった見える化も可能となるでしょう。
Create!Webフローは、紙をそのまま電子化して会社の規定のルート通りに上長に回すことのできるワークフローシステムです。電子化された書類上に押印も出来るうえに、証跡も残り、PDF保管もできるため、最終的に紙で印刷して今まで通り管理することも可能です。テレワークを推進している企業はぜひペーパーレス化にも目を向けてみてはいかがでしょうか。