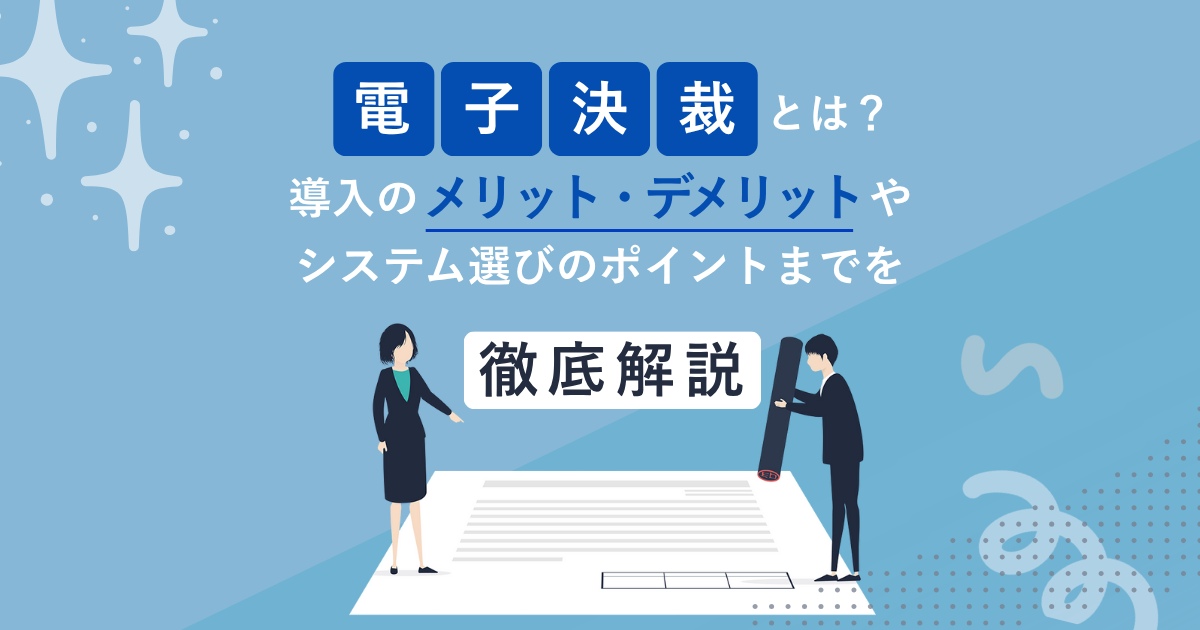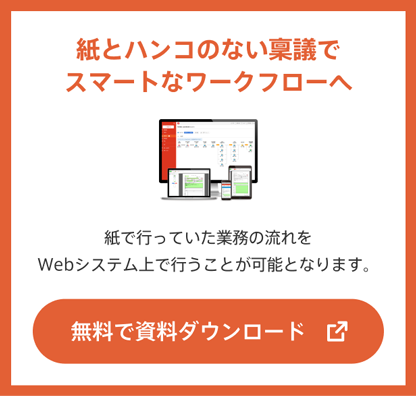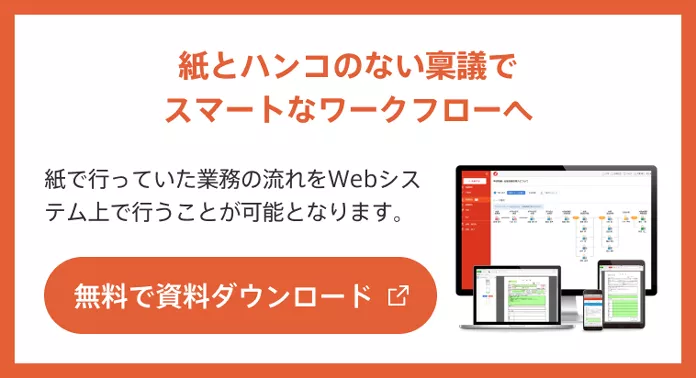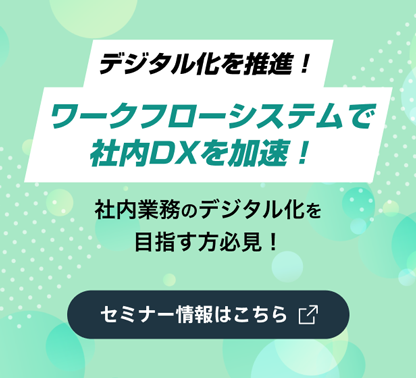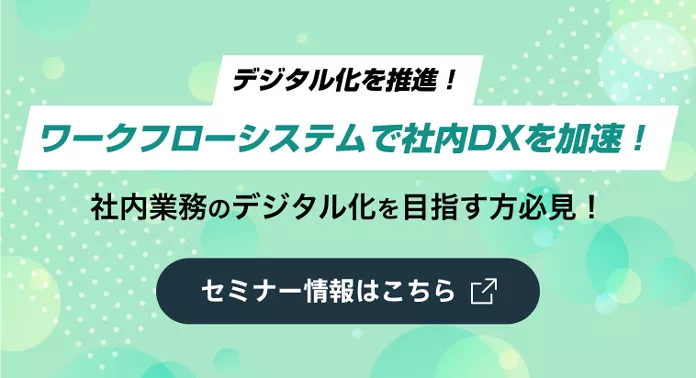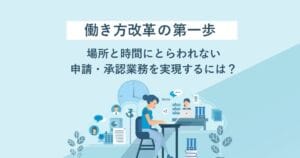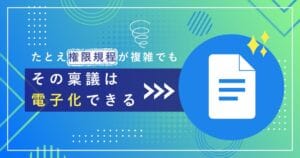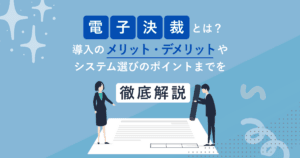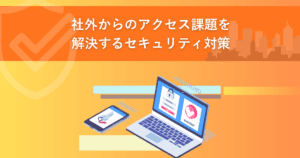電子決裁とは?導入のメリット・デメリットやシステム選びのポイントまでを徹底解説
近年多くの企業において、デジタル化の第一歩として、ペーパーレス化や脱ハンコといった業務の電子化が進められています。この取り組みを実現する上で欠かせないのが「電子決裁」です。
本記事は、この「電子決裁」について概要から導入のメリット・デメリット、さらにシステム選びのポイントまで詳しく解説します。電子決裁は単なる業務の電子化にとどまらず、企業全体の生産性向上や働き方改革にも寄与する重要な仕組みです。導入を検討している方はぜひ参考にしてください。
電子決裁とは?
電子決裁とは、これまで主に紙で行っていた申請・承認・決裁の一連のプロセスを電子化し、オンライン上で完結させる仕組みのことです。紙の書類や押印が不要になるため、オフィスに出社しなくてもスムーズに決裁処理が行えるようになります。
業務の流れ全体を電子化することから、ワークフローシステムとも呼ばれます。
電子決裁の基本機能
では電子決裁の基本機能を確認しましょう。決裁を効率的に進めるために主に以下のような機能が備わっています。
申請・承認機能
申請者は、必要な情報を入力し
承認者は、PCやスマホで申請内容を確認し、承認・却下・差し戻しなどの処理を実行します。最終承認者が承認を行うことで決裁手続きが完了し、決裁済みの書類は電子ファイルとして保存され、検索や閲覧が可能になります。通知機能
ユーザーが申請や承認を行った際にシステムが自動でメールやチャットに通知する機能です。承認の依頼や以前申請した案件が決裁されたことを確認することができます。 また、承認・決裁処理が滞っている場合、特定の承認者に対してメールやチャットで督促することもできます。
承認履歴
申請書の中に申請、承認、決裁、閲覧の各処理の履歴を記録し、証跡として残すことができます。
閲覧権限設定
申請したドキュメントについて、種類や内容に応じて、役職や所属グループごとに表示・非表示の閲覧権限を設定できる機能です。 決裁情報には機密性の高いデータが含まれるため、誰でも閲覧できないようにするためにアクセス権限を細かく設定できる機能が重要です。
電子決裁が求められる背景
このように様々な機能を持つ電子決裁ですが、なぜ今導入が進んでいるのでしょうか?電子決裁が求められる背景には、働き方やビジネス環境の変化が大きく関係しています。
テレワークの普及やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、業務の電子化が強く求められるようになりました。特に、2020年以降のコロナ禍を契機に、多くの企業がリモートワークを取り入れたことで、紙による決裁では対応できないケースが増えて電子決裁の導入が進みました。また、法改正による電子帳簿保存の義務化や、環境負荷軽減の観点からのペーパーレス化も電子決裁の導入を後押しする要因となっています。
電子決裁のメリット
では電子決裁を導入するメリットを確認していきましょう。主に以下のようなメリットが期待できます。
申請・承認の手間を削減
紙で決裁を進める場合は、印刷・押印・郵送・手渡しなど多くの工程が発生し、申請者・承認者双方の負担となります。
電子決裁なら、申請から承認までシステム上で完結し、物理的な移動が不要になります。さらに通知機能を活用すれば、承認漏れも防げるため、決裁から承認までの一連の流れをよりスムーズに進行することができます。また、検索性が向上して必要な書類をすぐに見つけられるため、業務効率も改善します。コストの削減
紙の使用には、紙代、印刷代、郵送費、保管コストが発生します。特に、大量の書類を扱う企業では、これらのコストが年間で数万円かかることがあり、企業によっては数十万円に達する場合もあります。 電子決裁を導入すれば、紙の使用が削減されるためこれらのコストを削減することができます。さらに、保管スペースの確保も不要になるため、オフィスの効率的な活用も実現できます。
テレワークに対応
紙で決裁を進めると申請や承認のためにオフィスに出社する必要があり、テレワークの障害となります。さらに、承認者が出張や休暇で不在の場合、決裁が滞るリスクもあります。 電子決裁を導入すれば、インターネット環境があればどこでも申請・承認が可能です。スマートフォンやタブレットからも承認できるため、承認者が出張に出ていても決裁を進められます。クラウド型のシステムを活用すれば、海外拠点ともスムーズに連携できるため、グローバルな業務展開にも適しています。
意思決定スピードの向上
企業にとって迅速な意思決定は競争力の向上につながります。しかし、紙の決裁では承認者が不在の場合や複数拠点への回覧が必要な場合などでは、承認プロセスが停滞することがあります。 電子決裁を導入すれば、紙の書類を物理的に承認者に届ける必要がなくなるため、決裁にかかる時間を大幅に短縮することができます。その結果、意思決定のスピードを向上させることができます。
内部統制の強化
紙の書類では、承認履歴が不明瞭になったり、紛失や改ざんのリスクが発生したりする可能性があります。 電子決裁なら、すべての決裁履歴がシステム上に記録され、承認の流れが可視化されるため、不正防止や監査対応が容易になります。また、アクセス権限を細かく設定できるため、機密情報の管理も強化できます。
情報の蓄積と共有による競争力強化
稟議書などの社内文書には、企業にとって重要な情報が含まれています。これらをシステム内で一元管理することで、社内資産として効率的に活用でき、組織全体の知見の共有や業務の最適化が可能になります。さらに、蓄積された情報を分析・活用することで、意思決定の精度向上や業務改善が進み、結果として企業の競争力強化につながると考えられます。
電子決裁のデメリット
このように多くのメリットがある電子決裁ですが、一方でデメリットもあります。導入にあたって注意すべき点も見ていきましょう。
初期導入コストがかかる
電子決裁の導入においては、システム購入費やカスタマイズ費用が必要です。自社の運用に合わせてカスタマイズ開発を行う場合は、開発する内容によってはコストが大きくかかる可能性があります。クラウド型のサービスであれば比較的安価に導入できるので、自社の運用フローを鑑みながら、クラウド型のサービスも検討しましょう。
決裁の運用ルールの見直しが必要
紙の決裁フローから電子決裁へ移行する際は、社内の業務プロセスを整理し、統一されたルールを確立することが重要です。従来の紙ベースの決裁では、部署ごとに異なる承認ルートや押印のルールが存在することが多く、そのまま電子化すると混乱を招く可能性があります。そのため、業務の流れを可視化し、不必要な承認ステップを削減するなど、最適なワークフローを設計することが求められます。
システムを使いこなせない従業員への対応
ITが苦手な従業員にとって、電子決裁システムの操作が難しく感じられることがあります。特に、長年紙ベースの業務に慣れている人にとって、新しいシステムへの適応には時間がかかる可能性があります。この問題を解決するためには、直感的に操作できるシステムを選ぶことが重要です。また、マニュアルの整備や定期的な研修を実施し、従業員が安心して電子決裁を利用できる環境を整えることが必要です。
セキュリティリスクへの対応が必要
電子決裁システムの導入によって、情報の一元管理が可能になりますが、データ流出や不正アクセスのリスクも考慮しなければなりません。特に、機密情報を扱う企業では、適切なアクセス制御やセキュリティ対策を講じることが重要となります。
電子決裁システム選びのポイント
以上のように電子決裁にはメリットだけでなくデメリットもあります。導入する際は達成したい目的から要件を整理して、その要件にあったシステムを選定することが成功のカギとなります。とはいえどの企業にも共通して重視すべきポイントもあります。以下、重視すべきポイントを5つ紹介します。
操作性がシンプルで使いやすいか
企業によって、業務フローは異なります。複数段階の承認が必要な場合や、部署ごとに異なる決裁ルールがある場合などは特に、柔軟に承認のフローを設定できるシステムかどうかを確認することが大切です。カスタマイズ性の高いシステムを選べば、よりスムーズに運用できます。
自社の業務フローに適応できるか
企業によって、業務フローは異なります。複数段階の承認が必要な場合や、部署ごとに異なる決裁ルールがある場合などは特に、柔軟に承認のフローを設定できるシステムかどうかを確認することが大切です。カスタマイズ性の高いシステムを選べば、よりスムーズに運用できます。
セキュリティ対策が十分か
電子決裁システムには機密情報が多く含まれるため、セキュリティ対策が重要です。安全に運用できる仕組みが整っているかを確認しましょう。特に、クラウド型のシステムを利用する場合は、提供会社のセキュリティ対策を事前にチェックしておくことが不可欠です。
サポート体制が充実しているか
PCの操作に不慣れな社員もいる場合は運用が軌道に乗るまでのサポートが重要となります。また緊急時やトラブルの際に迅速・的確に対応してもらえるかは、業務の停滞を防ぐうえで重要です。特に社内にITに詳しい人材が少ない場合、手厚いサポート体制の有無が安心して運用を続ける鍵となります。
導入実績は豊富か
様々な業種での導入実績が多いシステムは、多種多様な承認フローに対応できる柔軟性と安定性が期待できます。多くの企業に選ばれているという事実は、信頼性を判断するうえでも重要な指標となります。
まとめ
電子決裁は、企業の業務効率化やコスト削減に大きく貢献する仕組みです。導入することで、決裁スピードの向上、テレワーク対応といったメリットも得られます。ただし、初期導入コストや運用ルールの見直し、セキュリティリスクといった課題もあるため、慎重に検討する必要があります。
電子決裁システムを選ぶ際は、操作性、業務フローへの適応性、セキュリティ対策の充実度、サポート、実績などを重視し、自社に最適なシステムを導入しましょう。
電子決裁システムなら「Create!Webフロー」がおすすめ!
「Create!Webフロー」は直感的に操作ができ、様々な業務フローに対応しています。
Create!Webフローの特長
- 紙の見た目をそのまま電子化できるので、パソコンに不慣れな方でも紙に記入するイメージで直感的に操作が可能!
- 承認ルートを柔軟に設定できるので、自社の承認フローに合わせた運用が可能
- 人事異動の際などのメンテナンスも簡単に行え、管理者に専門知識がなくても使いやすいから自部門で運用できる
- 安心のセキュリティ対策(クラウド版)
- カスタマーサクセスチームによる運用支援や活用推進サイトなど、Create!Webフローをご活用いただけるよう様々なサポートを用意
- 製造業や情報・サービス業、さらに学校法人など多種多様な業種への導入実績
Create!Webフローによって電子化に成功した事例
事例①AOSデータ株式会社様 (従業員数100人未満)
「上場を見据えた内部統制の強化へ」
課題
IPOを目指す中、承認・決裁プロセスが紙ベースで行われており、承認プロセスが不明確で記録も残らず、内部統制の面で懸念があったそうです。また、従来の運用を大きく変えてしまうと業務負担が増す可能性があり、社内からの反発が危惧されていました。
導入効果
ワークフローシステムの導入により承認・決裁業務の流れが整ったため、 内部統制を強化することができたそうです。さらに決裁にかかる時間が短縮されて、意思決定スピードも向上し、ハンコを押すための出社も不要となり、テレワークも推進されたそうです。
選定理由
スモールスタートで試験的に運用開始してみたところ、既存の紙イメージを踏襲したUIや、マニュアル不要で直感的に使える操作性から、現場の社員が負担なく電子化できると判断されて、導入いただきました。
事例②アサヒ飲料株式会社様 (従業員数1,000人未満)
「意思決定が7日間短縮し、4000時間分のコストカットを実現」
課題
紙の稟議書を次々に回覧していくやり方のため、関連の各部署を7~10ヶ所ほど回覧し、決裁が下りるまで3週間~1ヶ月を要していたそうです。そのため意思決定に時間がかかるうえに、回覧に費やす時間や保管スペースのコストもかかっていたそうです。また決裁の進捗状況確認も手間となっていたそうです。
導入効果
導入により、稟議時間を短縮でき、回覧・保管にかかるコストも削減できたそうです。さらに文書管理システム「ArcSuite Office」と連携し、素早く稟議書検索ができるようになったそうです。また業務の標準化や内部監査の効率化も実現できたそうです。
選定理由
紙のイメージを重視すること、操作性の良さ、押印ができることが選定の要件となったそうです。Create!Webフローはこれらの要件を満たしていて、さらに承認ルートの自由度が高く、低コストで、印影の登録が簡単にできることを評価されて、選定いただきました。
事例③高崎商工会議所様 (行政・公共機関)
「ペーパレス化 で年間6,000枚以上の紙を削減」
課題
高崎商工会議所では補助金の申請支援を行う際は必ず稟議を挙げていて、コロナ禍により事業者からの補助金相談が急増するなか、膨大な紙書類の処理や保管場所の確保に困るようになったそうです。しかし既存のグループウェアでは添付ファイルの閲覧等の使い勝手に課題がありました。
導入効果
進捗状況が確実に把握できるようになり、紙書類の紛失や処理忘れを回避でき、処理が止まった理由もコメントとして残せるようになりました。また稟議を回すのに1件当たり10枚以上の紙書類を印刷していたので、約6,000枚の紙を削減でき、導入目的の保管場所の問題も紙書類の整理が進んでいるそうです。
選定理由
既存の紙書類をそっくりそのまま再現でき、ITに詳しくない職員もフォームや承認ルートを容易に作成できることや、承認ワークフローの添付ファイルを紙書類をめくる感覚で閲覧できることも評価頂きました。インフラ管理が不要なクラウドサービスとして提供している点も選定理由となりました。
事例でご紹介したように、「Create!Webフロー」なら、電子決裁の導入をスムーズに進めることができ、紙の書類を使った従来の決裁プロセスを効率化できます。直感的な操作性や柔軟な承認ルートの設定機能を備えており、社内の業務フローに合わせた最適な運用が可能です。また、決裁のスピードアップにより、迅速な意思決定をサポートし、業務全体の生産性向上にも貢献します。
電子決裁を導入して業務改善を目指している方は、ぜひ以下より「Create!Webフロー」の資料をダウンロードして、詳細をチェックしてみてください。